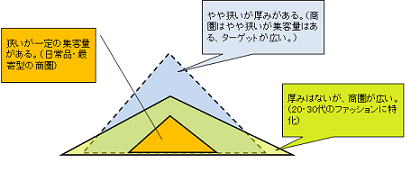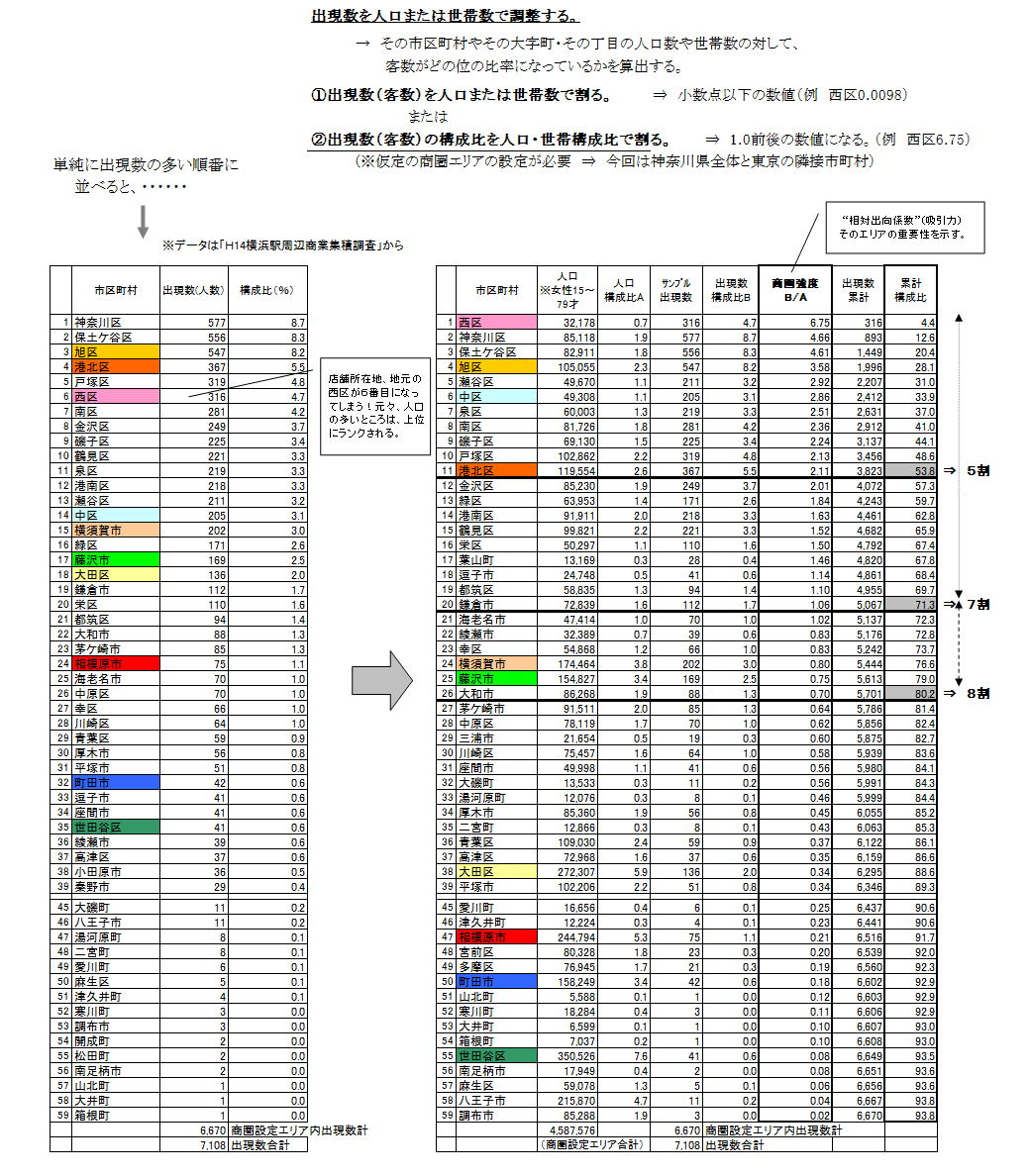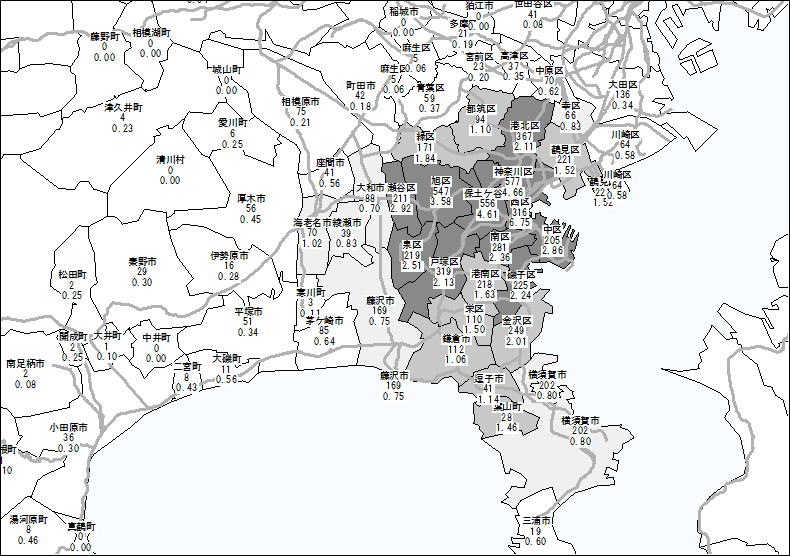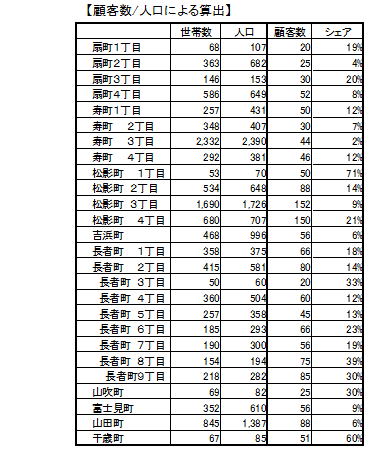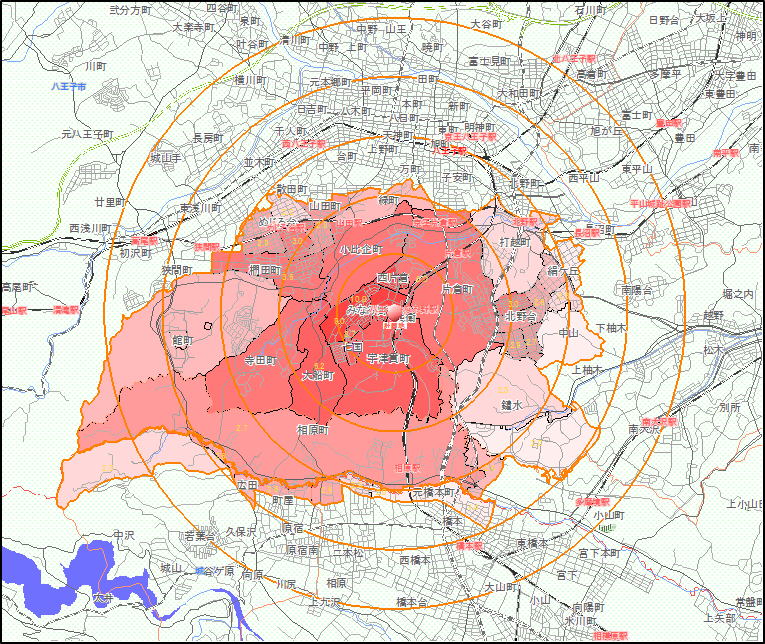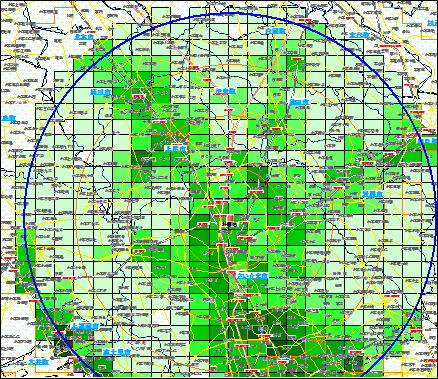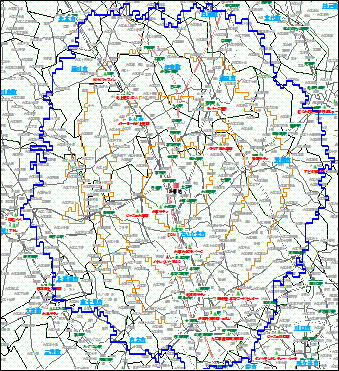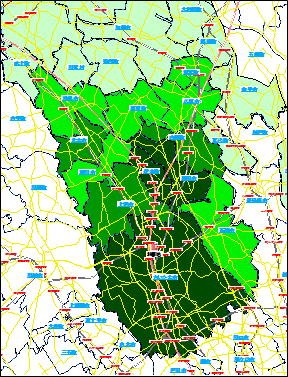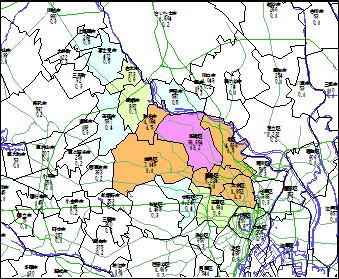|
2.商圏の設定
商圏を設定される際、“実態の商圏”で設定するのか、また“戦略的な意図”を持って、商圏設定をするかで内容が違ってきます。
一般的に「商圏」と行った場合、「実態の商圏」のことです。戦略商圏は、「実態の商圏」の把握した後、「戦略的な意図」を持って「戦略エリア」
を加える。
a)設定基準
基本的な「実態商圏」の分類について「設定の基準」の紹介
標準的な設定方法は、顧客の分布数を基に商圏を把握する方法が一般的です。以下、設定基準について紹介しますが、これまでの
経験からみるとこれが正解というものはありませんので、その都度判断しています。
私の個人的に設定方法は、お客様にわかりやすいように、ぉ客様居住地者の累計5割のエリア、累計7割のエリア、累計8割のエリアなど
累計構成比を示すようにしています。
<中小企業庁編の商圏>
[売上・客数の構成比を求める方法]
1次商圏 ⇒ 売上または客数の60%程度以上を占める顧客の範囲
2次商圏 ⇒ 1次商圏以遠で売上または客数の30%程度以上を占める顧客の範囲
3次商圏 ⇒ 2次商圏以遠で売上または客数の5%程度以上を占める顧客の範囲
[その地域からの需要で求めるやり方]
1次商圏 ⇒ 商圏内消費需要の30%以上を吸収しているエリア
2次商圏 ⇒ 商圏内消費需要の10%以上を吸収しているエリア
3次商圏 ⇒ 商圏内消費需要の5%以上を吸収しているエリア
<牛窪氏>
1次商圏 ⇒ 顧客の68%が集中しているエリア
2次商圏 ⇒ 顧客の27%が 〃
3次商圏 ⇒ 顧客の5%が 〃
<渥美氏>
特定の1店舗への来店見込み客の8割が居住している地域
<USAスーパーマーケット>
1次商圏 ⇒ 70%
2次商圏 ⇒ 25%
3次商圏 ⇒ 5%
<その他>
[その地域からの出向率で求める方法]
1次商圏 ⇒ 来店頻度が週2回以上
b)設定に使うデータ
①市場調査によるデータ
・退店客に対し、自記式調査や面接調査で住所を質問する。 ⇒ 「丁目くらいまで質問」
・小さな郊外店(SC)であれば、500サンプルくらいで可
・土曜日や日曜日など、その店舗の商圏が広くなるときに調査を実施するのが好ましい。 (折り込みチラシを実施した土曜日など)
②既存の名簿データによるもの
顧客名簿・ポイントカードの住所・プロモーション参加者の住所など
◆ポイントカードホルダーの名簿
・最近その店を利用していない方の名簿は、なるべく除外する。(最近利用のない人 ⇒ お店の内容で、その都度検討)
・利用金額などのデータが付帯してあれば、商圏の特徴がよくわかる。
※カードホルダーなどで、支出金額総額などがわかれば、その金額でも可。
◆プロモーションの参加名簿など
・プロモーションの内容によっては、名簿が偏っている可能性があるので注意。
・その店の利用者全体をターゲットにしたプロモーション名簿をなるべく利用する。
|